貸店舗の内装制限とは?建築基準法に違反しないための基礎知識

-
内装制限とは|わかりやすく解説
-
内装制限を守らないとどうなる?
-
自分の店が対象か知りたい!内装制限のチェックポイント3つ
-
内装制限の対象だったときの対処法
-
建築基準法における内装制限の具体例
-
開業前に確認したい!内装制限のチェックポイント
-
まとめ
内装制限とは、「火災が発生したときのためのルール」です。
たとえば、もし店舗で火災が起きたとき、壁や天井に燃えやすい素材が使われていたら、一気に火が広がり、お客様や従業員の命を危険にさらしてしまうかもしれません。
そうした事態を防ぐため、建築基準法や消防法では「燃えにくい材料」を内装に使うルールがあります。これが「内装制限」です。
特に、不特定多数の人が出入りする飲食店、美容室、物販店などの店舗では、内装制限の対象になるケースが多いため注意が必要です。
内装制限は2つの法律がある
実は、内装制限は建築基準法だけでなく、消防法でも定められています。
どちらもお客様をはじめ、従業員など様々な人の命を守るために大切な法律です。
建築基準法における内装制限
建築基準法の内装制限は、火事が発生した時の安全避難を目的としています。火災が広がって避難経路が塞がれたり、有害なガスが発生しないように内装材料に様々な制限を設けています。
建物の延焼を防ぐ素材で燃え広がりを防ぎ、避難経路を確保しやすくするためのルールです。
消防法における内装制限
消防法の内装制限は、火災リスクの軽減や消化活動などの防火を目的としています。消火栓の設置や燃えにくい素材の使用を義務づけています。
火災を未然に防いだり、発生時の初期消火や本格的な消火活動をしやすくするためのルールです。
内装制限を守らないとどうなる?
内装制限を守らずに店舗をオープンすると、後から是正指導を受けたり、最悪の場合は営業停止になることも。
開業前にしっかり確認しておくことが大切です。
「知らなかった」では済まされない
内装制限は、知らなかったからといって免除されるものではありません。
内装工事を行う際は、施工主(=テナント)が責任をもって法令を確認する義務があります。
内装制限に違反していたことが後から判明した場合、「ここを修正してください」という是正命令が出たり、最悪の場合は営業停止になる可能性も。
とくに飲食店や美容室などでは開業前の検査が厳しくチェックされるので、オープン直前に「やり直し」と言われて慌てるケースも少なくありません。
オーナーや管理会社から修繕費用を請求されるケースもあり、知らなかったでは済まされないトラブルに発展することもあります。
自分の店が対象か知りたい!内装制限のチェックポイント3つ
内装制限の対象かどうかは、建物の種類と構造によって決まります。
以下の1~3の順番で確認してみましょう。
まず1.「特殊建築物」に当てはまるかを確認し、2.その上で建物の耐火構造をチェックします。
さらに、3.特殊建築物でなくても一定の条件を満たすと内装制限の対象になる場合があります。
1.ほとんどの店舗が該当!?まずは「特殊建築物」に当てはまるか確認!

「特殊建築物」は建物の用途によって決まります。
病院やカフェ、ホテルなど多くの人が出入りする建物や火を使用する店舗など、貸店舗の多くが対象となります。
●劇場・映画館・劇場・集会場など
●病院・診療所・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・こども園など
●百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・バー料理店・公衆浴場など
●地階または地下工作物内の部屋などで上記の用途で使用する部屋がある場合
●自動車車庫・自動車修理工場・映画スタジオ・テレビスタジオなど
2.次に、耐火構造の種類をチェック!

建物の「耐火構造」は3つのタイプに分かれます。どのタイプかによって、内装制限の対象かどうかが変わります。
耐火建築物
主要な部分に高い耐火性能のある素材が使われている建物。
準耐火建築物
耐火建築物ほどではないけれど、ある程度の耐火性能がある建物。
その他の建築物
上の2つに当てはまらない建物。
3.「特殊建築物」に当てはまらなかった場合も要注意!
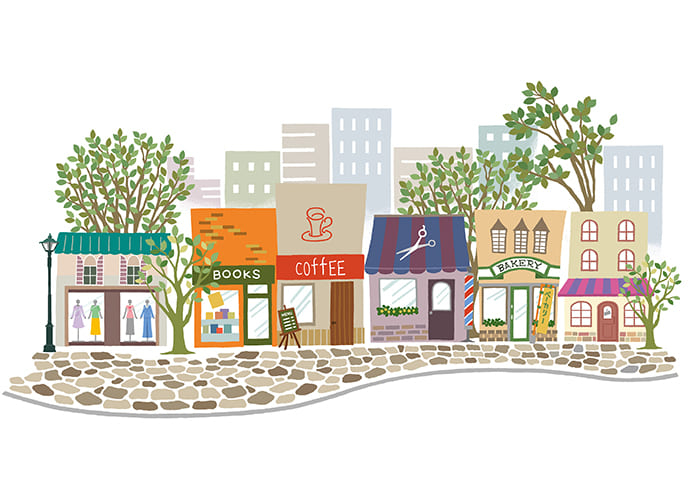
特殊建築物に当てはまらなくても内装制限の対象となる建物があります。
特殊建築物かどうかだけで判断すると危険なので、必ず下記の条件に当てはまるかどうかも確認しましょう。
●3階以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
●2階で延べ面積が1,000㎡を超えるもの
●1階で延べ面積が3,000㎡を超えるもの
●政令で定める窓(採光を取り入れるための窓または開口部)がない部屋
●調理室、浴室など火を使う部屋
対象かどうかを正確に調べるには、日本室内装飾事業協同組合連合会(日装連)の内装制限一覧表をチェックするのがおすすめです。
たとえば、カフェが「耐火建築物」の場合は、3階以上の床面積が合計1,000㎡以上なら内装制限の対象になります。
借りたい物件が対象かどうか、しっかり確認しておきましょう。
そのほか、地域によっては、都道府県独自の内装制限ルールを設けている場合もあります。
迷ったときは、必ず自治体や専門業者に確認しましょう。
内装制限の対象だったときの対処法
内装制限の対象であった場合は、慌てずに対処しましょう。
ここでは、内装制限に対応するために押さえておきたい4つのステップを紹介します。
1.必要な安全設備を整える
内装制限のある店舗では、安全設備の設置が義務づけられるケースがあります。たとえば以下のようなものです。
●消火栓の設置
火災発生時に備えて、建物の用途や規模に応じた消火栓が必要です。
特に人の出入りが多い施設では、法律に従って正しい位置に設置・管理することが求められます。
●排煙設備の設置
床面積が500㎡を超える特殊建築物や、3階以上で500㎡を超える建物には排煙設備の設置が義務づけられます。
煙の排出によって視界の確保・有毒ガスの拡散防止など、安全な避難に役立ちます。
●その他の設備
消火器や自動火災報知器なども必要になることがあります。
とくに地下や窓のない物件では煙がこもりやすいため、こうした設備の設置が必須になることも多いです。
2.使える内装材を選ぶ
内装制限がかかると、壁・天井などの素材選びにも制限が生じます。建築基準法では、以下のような材料が定められています。
不燃材料(NM-〇〇〇〇)
加熱しても燃えない、または燃えにくい素材。
建物の安全性を最も高められます。
準不燃材料(QM-〇〇〇〇)
過熱後10分間は燃えない素材。
時間を稼いで避難の安全性を確保する目的があります。
難燃材料(RM-〇〇〇〇)
過熱後5分間は燃えない素材。
不燃・準不燃に比べて制限が緩やかですが、ある程度の耐火性が必要な場所に使われます。
素材にはラベルやカタログに「国土交通大臣の認定マーク」がついているので、選ぶ際は必ず確認しましょう。
また、クロスや木材などの仕上げ材だけでなく、壁の下地材にも基準が適用されるため、内装業者に「ここは内装制限あり」と伝えておくと安心です。
3.物件の構造に応じた対応を考える
内装制限の厳しさは、建物の構造によっても変わります。特に注意が必要なのは以下のような物件です。
●地下店舗
●窓のない閉鎖空間
こうした場所は避難が難しいため、通常よりも厳しい基準が適用されます。
たとえば、ドアや間仕切りにまで不燃性の素材が求められたり、排煙ダクトの設置が義務化されていたりします。
後から「使いたい素材が使えなかった」と困らないよう、最初の段階で建築士や消防署に確認しておきましょう。
4.専門家と連携して進める
内装制限があるからといって、必ずしも「高コストで大変」と決まっているわけではありません。
条件によっては制限が緩和されるケースもありますし、意外と対応可能な場合も多いです。
ただし、これを自己判断で進めるのは難しいため、設計士・内装業者・建築士といった専門家に相談しながら、正しい判断と施工を進めましょう。
最初の段階からプロと連携することで、無駄な手戻りを防げて、スムーズにオープン準備ができます。
建築基準法における内装制限の具体例
建築基準法では、次のような建物・テナントが内装制限の対象になりやすいです。
●不特定多数が利用する施設(飲食店、美容室、小売店など)
●地下にある、または避難経路が少ない建物
●延べ面積が一定以上ある建物(目安として150㎡以上)
●テナントビルや複合施設の中にある場合
これらに該当する場合、店舗の用途や場所に関わらず、壁や天井に「不燃・準不燃素材」を使う義務が出てくる可能性があるので注意が必要です。以下に具体例を2つ紹介します。
■火を使用する飲食店や店舗の場合

カフェやレストランなど火を使用する飲食店の場合をご紹介します。耐火構造ごとの基準に当てはまった場合、以下の対応が必要となります。
①居室等は壁が難燃以上(床面上1.2m以下除く)、天井が難燃以上(3階以上に居室を有するものは準不燃以上)の内装材料を使用
②通路・階段等は壁・天井とも準不燃以上の内装材料を使用
■地下階にある居酒屋など、窓がない屋内密閉空間で地下の場合

店舗が地下階にある場合は、窓がない構造であることが多く、内装制限がより厳しくなります。以下の対応が必要です。
①居室・通路・階段等すべての壁および天井に、準不燃以上の内装材料を使用
②窓がないため、通常であれば難燃以上で済む部分も、準不燃以上に変更が必要
③1階と地下階が繋がっている構造の場合、1階で使用可能な内装材を地下に流用すると基準違反となる可能性があるため注意
開業前に確認したい!内装制限のチェックポイント
物件選びや内装工事を進める前に、「この店舗は内装制限の対象かどうか」をチェックすることが重要です。
後から工事のやり直しや営業許可の遅れを防ぐために、以下のポイントを事前に確認しておきましょう。
事前に確認したい「建物の構造・用途」
まず最初に確認したいのが、建物の構造(木造・鉄骨造など)と、用途(商業施設、共同住宅など)です。
たとえば、「木造の古い建物」と「鉄骨造の新しいテナントビル」では、内装制限の条件が全然違うことも。
不動産会社やオーナーから物件資料をもらう際に、「この建物は内装制限の対象になるか」を聞いておくとスムーズです。
オーナー・管理会社への相談も忘れずに
物件によっては、オーナーや管理会社があらかじめ素材指定していることもあります。
「この壁紙は使わないでください」「この工事は許可がいります」など、細かなルールがある場合も。
事前にしっかり相談しておけば、トラブルや工事中断を防ぐことができます。
内装業者に必ず伝えるべきこと
内装工事を依頼する業者には、以下の情報を必ず伝えておきましょう。
・建物が内装制限の対象であること
・地下や窓のない区画であるかどうか
・飲食店など火を使う業態であるかどうか
内装業者がこういった情報を知らずにプランを進めると、「あとからやり直し」や「消防検査でNG」になるリスクが高まるので要注意です。
保健所や消防署のチェックにも注意
店舗を開業する際には、保健所や消防署のチェックも必要になります。
このとき、「壁や天井が不燃材・準不燃材かどうか」など、内装の素材まで細かく見られる場合があります。
開業直前に素材を変える羽目になった…なんてことを防ぐためにも、物件契約後すぐに内装制限の確認をスタートしましょう。
まとめ
店舗づくりは見た目だけでなく、万が一の際の「安心・安全」も大切です。
貸店舗で内装工事をするなら、「内装制限」という建築基準法のルールをしっかり理解しておきましょう。
●内装制限とは「火災時に燃え広がらないためのルール」
●壁・天井には不燃または準不燃素材が必要になるケースあり
●違反すると是正命令や営業停止、オーナーとのトラブルも
●地下店舗や窓のない空間はさらに厳しい対応が必要
●施工前に、物件の構造・用途・業者・管理会社への確認が必須
ルールを守って、スムーズに開業するのだ~!

- ニッショー.jp
- サガッシーのなるほどふむふむ
- 貸店舗の内装制限とは?建築基準法に違反しないための基礎知識




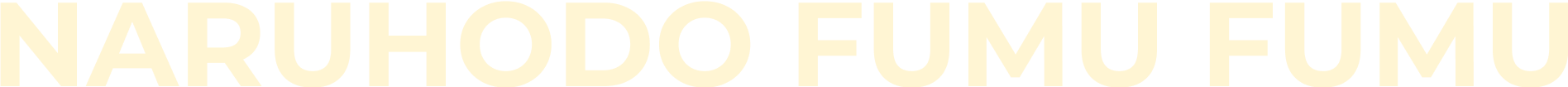

愛知・岐阜・三重で50年以上、地域密着の直営主義でお部屋探しを提供している不動産会社【ニッショー】が運営するWebマガジン。
思わず「なるほど〜」「ふむふむ」とうなずけるようなイチオシ情報をサガッシーとともにお届けします!











