線路沿いの家はやめた方が良い?後悔しないためのチェックポイント8選

-
線路沿いの家はやめとけと言われる理由【デメリット5つ】
-
線路沿いの家は実際どこまでうるさい?音と振動の範囲
-
線路沿いの家に住んで後悔しないためのチェックポイント8選
-
線路沿いの家でも快適に過ごすための対策
-
線路沿いの家はどんな人に向いている?
「線路沿いの家はやめとけ」と言われることがありますが、その理由は何でしょうか。
ここでは、線路沿いの家の代表的なデメリットを5つ紹介します。
1.騒音レベルが想像以上にうるさい

電車や車両の音、警笛の音が常に響き、特に夜中や早朝に気になることが多いです。住んでみると、その音の大きさや頻度に驚くことも。
騒音は心身にストレスを与えることがあり、慣れるのに時間がかかる場合もあります。
2.振動が不快

音だけでなく、電車が通るたびに地面が揺れ、振動が不快に感じることがあります。
振動が原因で家具が揺れたり、寝ているときに起こされたり、特に敏感な人にとっては大きなストレスになります。
寝不足やイライラが続くと、ノイローゼや不安障害の原因になることも。
3.健康リスクが心配
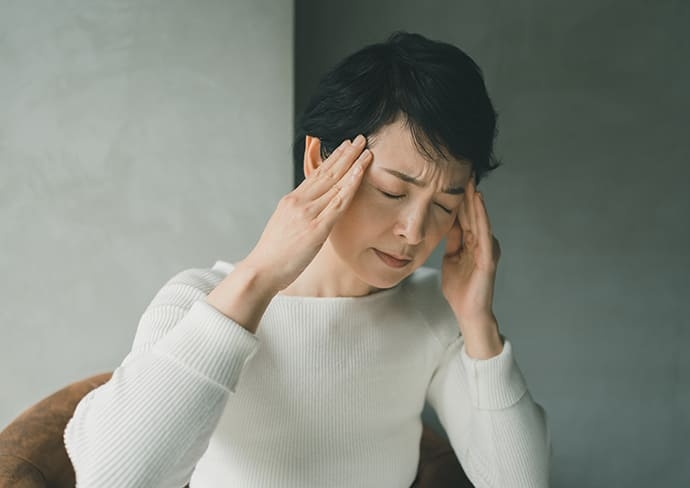
人によっては、電磁波による体調不良を引き起こす人もいます。
また、長期間接することで、電磁波が健康に悪影響を与えるのではないかと心配する人もいます。
これらの懸念は、実際には科学的根拠が不十分ですが、少なくとも気持ちの面で体調や健康への不安を感じるのであれば、選択肢から外すのも一つの方法です。
4.線路沿いの家は不幸を招くといわれる

スピリチュアル的な観点では、線路沿いの家は「不運を招く場所」と言われることもあります。
一方、風水では、線路の電磁波や高速で動く電車の影響で気の流れが乱れ、運気が下がると考えられています。
こうした考えを気にする人にとっては、心理的なストレスにつながることも。
スピリチュアルな意見をどこまで重視するか、事前に考えておくのも大切です。
5.精神的にノイローゼになることも

騒音や振動に対する耐性は人それぞれですが、長期間にわたり不快に感じると、精神的な健康に悪影響を及ぼす可能性もあるので注意が必要です。
初めは「慣れれば大丈夫」と思っていても、時間が経つにつれてストレスが蓄積され、後悔することも。
賃貸でも購入でも、実際に住んでみてから騒音や振動に耐えられなくなるケースが多いです。
特に転職や生活環境が変わると、思っていたよりも大きなストレス源になることがあります。
線路沿いの家は実際どこまでうるさい?音と振動の範囲
電車の通る音や振動は、線路に近い家だけでなく、意外と離れた場所まで影響を及ぼすことがあります。
どれくらいの距離まで影響があるのか、また、建物の条件によってどのように変わるのかを確認しておきましょう。
音の影響範囲
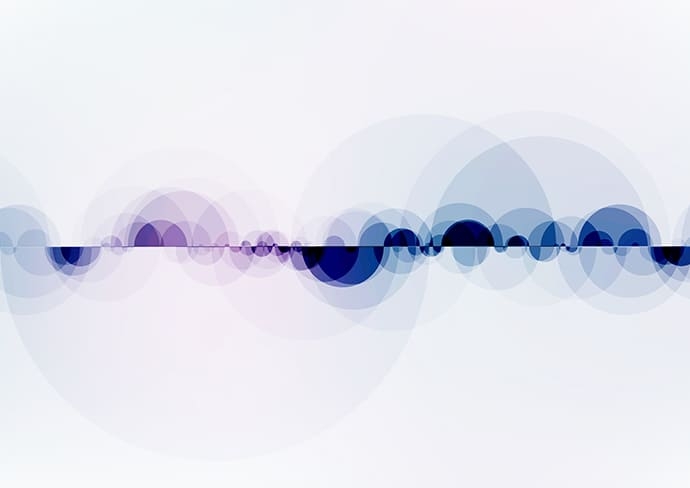
電車の走行音は、環境によって異なりますが、一般的に500m以上離れた場所でも聞こえることがあります。
特に、夜間や早朝の静かな時間帯は、日中よりも音が響きやすい傾向があります。
-
- 騒音レベルの目安
- 目安として、新幹線や貨物列車が通る路線では100m以内の距離だと、窓を閉めてもかなりの音が聞こえることが多いです。
住宅地を走る在来線でも、50~100m圏内では会話に影響するレベルの騒音になることがあります。
-
- 周囲の環境による違い
- 開けた場所では音が遠くまで届きやすく、防音壁や高架がある場所では多少軽減されます。
また、駅の近くでは発車・停車時のブレーキ音やアナウンスの音が響くため、走行音とは違う騒音の問題も発生します。
-
- 天気や時間帯の影響
- 雨の日や湿度が高い日は音が遠くまで伝わりやすく、夜間は他の騒音が少ないため、よりはっきりと聞こえることがあります。
振動の影響範囲
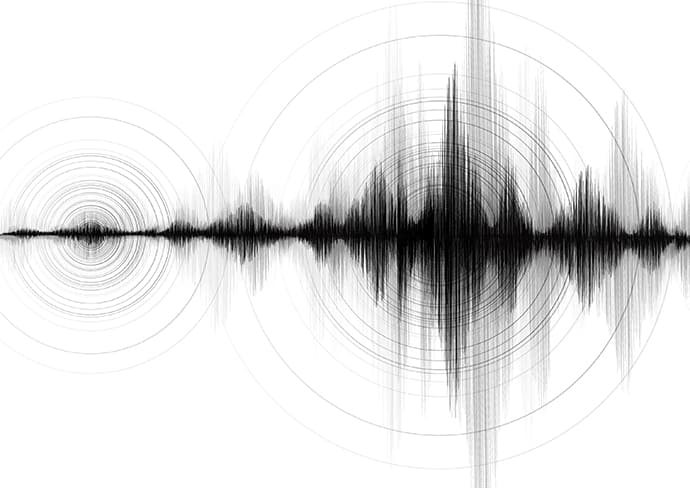
電車の振動は、家の構造や地盤の状態によって大きく変わります。
線路沿いに住む場合、実際にどれくらいの振動が伝わるのかを確認することが重要です。
また、建物の線路側に面した部屋と、反対側の部屋では振動の感じ方が大きく異なる場合もあります。
-
- 距離による影響の違い
- 振動は、線路から30m以内では特に強く感じることが多いです。高架下や線路に近い建物は影響を受けやすく、場合によっては家具や窓がわずかに揺れることもあります。
50m以上離れると振動の影響は弱まりますが、地盤の状況によっては100m以上でも感じることがあります。
-
- 建物の構造による違い
- 鉄筋コンクリート造のマンションは比較的振動を吸収しやすく、木造や軽量鉄骨の住宅では、振動が伝わりやすくなる傾向があります。
特に築年数の古い物件は、振動の影響を受けやすいことがあるので注意が必要です。
-
- 部屋の位置と影響の違い
- 1階や地面に近い部屋は振動を受けやすく、上層階になるほど影響が軽減されることが多いです。
また、建物の線路側に面した部屋と、反対側の部屋では振動の感じ方が大きく異なる場合もあります。
線路沿いの家に住んで後悔しないためのチェックポイント8選
ここでは、線路沿いの家に住んで後悔しないために確認しておきたい8つのポイントを「物件内」と「周辺環境」に分けて紹介します。
自分の生活スタイルに合った環境かどうかをしっかりチェックして、納得のいく住まい選びをしましょう。
物件内で確かめること
1.電車の音が気にならないか
2.振動が部屋に伝わらないか
3.洗濯物が外に干せそうか
周辺環境で確かめること
4.駅までのアクセスはしやすいか
5.踏切や駅周辺は渋滞するか
6.事故が多くないか
7.電車の本数が多すぎないか
8.線路以外に騒音がないか
1.電車の音が気にならないか
内見時は、窓を閉めた状態で電車の音を確認し、すべての部屋で聞こえ方をチェックしましょう。
特に寝室やリビングで音が気にならないかが最も重要です。
二重サッシや防音カーテンなどの設備も確認し、防音対策がされているかも確認しましょう。
角部屋や上階のほうが騒音が軽減される場合もあるため、物件の構造もしっかりチェックしましょう。
2.振動が部屋に伝わらないか
電車の通過時に床や壁が微妙に揺れる物件もあるので、実際に電車が通るタイミングで体感しておきましょう。
特に貨物列車が通る路線は、重さの影響で揺れが大きくなることがあります。
また、リラックスしたい空間で振動を感じると不快なので、揺れを感じる場合はどのくらいの影響があるかも確認しましょう。
3.洗濯物が外に干せそうか
線路沿いは、電車の風圧で細かい砂ぼこりが舞ったり、排気ガスの影響で洗濯物が汚れたりすることも。
ベランダの手すりや窓のレールに汚れが溜まりやすいか確認し、影響を受けやすいかどうかチェックしておきましょう。
4.駅までのアクセスはしやすいか
線路沿いでも、駅までの距離や経路は物件によって異なります。例えば、駅まで行くのに踏切を渡る必要があると、想像以上に時間がかかることも。
実際に歩いて、通勤・通学に負担がないか確認しましょう。
5.踏切や駅周辺は渋滞するか
踏切の場所によっては渋滞や遠回りが発生することがあります。
特に通勤・通学時間帯は交通量が増えるので、実際に現地で様子を確認しておきましょう。
踏切の開閉時間が長いと、移動のストレスになる可能性も。
6.事故が多くないか
フェンスの有無や、子どもやペットが誤って近づける場所がないかを確認しましょう。
線路や踏切に安易に近づけないようになっていれば安心ですが、人身事故が多い場所では、精神的な負担や電車の遅延リスクが増えてしまいます。
口コミやニュースなどで情報を集めてみるのも良いでしょう。
7.電車の本数が多すぎないか
電車の本数が多いと通勤通学に便利ですが、家にいるときには騒音や振動が日常的に発生することになります。
深夜や早朝の運行状況、貨物列車の有無も確認し、日常生活に影響しないかチェックしましょう。
普段は静かでも、休日や夜間に本数が増えることがあるので注意が必要です。
8.線路以外に騒音がないか
騒音の原因はさまざまです。例えば幹線道路や工場、大型トラックが通る道、深夜営業の店などが近くにあると、昼夜で騒音の感じ方が大きく変わることもあります。
そのため、線路沿いだけでなく、他の騒音源も確認し、時間帯を変えて現地でチェックすることが大切です。
線路沿いの家でも快適に過ごすための対策
ここでは、線路沿いの家によくあるデメリットについて、4つの具体的な対策を紹介します。
音や揺れがストレスになる可能性があるため、快適な暮らしのために適切な対策をとりましょう。
1.防音対策
電車の走行音や踏切の警報音を軽減するには、防音対策が重要です。
-
- ●遮音カーテンを使う
- 厚手の遮音カーテンを窓に設置することで、室内に入る音を軽減できます。特に窓が線路側にある場合は有効です。
-
- ●窓の防音フィルムを貼る
- 防音フィルムを窓ガラスに貼ることで、外からの音の侵入を和らげる効果が期待できます。
-
- ●二重窓・防音サッシに変更する
- 二重窓や防音サッシに変更できれば、防音効果を大幅にアップできます。
-
- ●家具の配置を工夫する
- 窓の前に本棚や収納家具を置くことで、音の反響を抑えることができます。
2.振動対策
電車が通るたびに家が揺れるのを防ぐには、家具や建物の工夫が必要です。
-
- ●耐震マットを敷く
- 家具の下に耐震マットを敷くことで、揺れが直接伝わるのを軽減できます。
-
- ●床にカーペットやラグを敷く
- 床に厚手のカーペットを敷くことで、振動を吸収しやすくなります。特にフローリングの場合は効果が大きいでしょう。
-
- ●防振ゴムを使う
- 家具の脚に防振ゴムをつけることで、細かな振動が伝わりにくくなります。
3.電磁波対策
電車の走行によって発生する電磁波が気になる場合は、以下のような対策を考えましょう。
-
- ●寝室の配置を工夫する
- 線路側に寝室を設置すると、電磁波の影響を受けやすい可能性があるため、できるだけ反対側の部屋を寝室にするのがおすすめです。
-
- ●電磁波カットカーテンを使う
- 電磁波を軽減する特殊なカーテンを使うことで、電磁波の影響を和らげることができます。
-
- ●家電の配置を工夫する
- 家電からも電磁波が発生するため、電子レンジやWiFiルーターなどの電磁波が強いものは寝室の近くに置かないようにしましょう。
4.ホコリ対策
線路沿いの家は、車両の走行によって道路のほこりや排気ガスが舞いやすく、室内にほこりが溜まりやすくなることがあります。これを防ぐためには、以下の対策を取り入れると効果的です。
-
- ●窓の密閉性を高める
- 線路側の窓は、窓の密閉性を高めることが重要です。
二重窓や防音・防塵フィルムを使うことで、ほこりの侵入を軽減できます。
-
- ●換気の工夫
- 換気が必要な場合でも、外のほこりをなるべく入れないように工夫しましょう。
例えば、換気口にフィルターを取り付けたり、外の空気を取り入れる時間帯を工夫したりして、ほこりが少ない時間に換気を行いましょう。
-
- ●エアコンや空気清浄機を活用する
- HEPAフィルター付きの空気清浄機を使うと、細かいほこりも除去でき、室内の空気が清潔に保たれます。
また、エアコンのフィルターも定期的に掃除して、ほこりが室内に回らないようにしましょう。
-
- ●こまめな掃除
- ほこりがたまりやすい場所は、こまめに掃除をしましょう。特に窓のサッシやエアコン周り、家具の上などは、定期的に拭き掃除をすると良いでしょう。
-
- ●カーテンや布製品の洗濯
- 窓際に置いているカーテンや布製品は、ほこりを吸いやすいので定期的に洗濯することが大切です。
特に布製のカーテンはほこりを絡めやすいため、乾燥機や風通しの良い場所でしっかりと乾かしましょう。
線路沿いの家はどんな人に向いている?
線路沿いの家はどんな人に向いているのか、具体的に見てみましょう。
●駅近に住みたい人

線路沿いの家のメリットの一つは、徒歩圏内に駅がある物件が多く、駅までのアクセスが良いことです。
駅近の便利さを優先する人にとってはぴったりの環境です。
メリット
●通勤・通学が楽
駅までの距離が短いため、朝の通勤時間を短縮できます。
●帰りが遅くても安心
駅から近いと夜遅くなっても帰宅しやすく、防犯面でも安心感があります。特に女性や夜勤のある人にはメリットが大きいでしょう。
●雨の日の移動がラク
駅までの距離が短いため、天候が悪い日でも移動がスムーズです。傘をさして歩く時間が少なくなるのも魅力です。
●家賃を抑えたい人

線路沿いの家は、同じエリア内でも家賃が安く設定されていることが多いです。
音や振動といったデメリットがある分、相場よりもリーズナブルな価格で住めるのが魅力です。
メリット
●広めの物件を選べる
駅近で家賃を抑えようとすると狭い部屋になりがちですが、線路沿いなら同じ家賃でも間取りに余裕のある物件が見つかる可能性があります。
●貯金や趣味に回せる
家賃を抑えることで、浮いたお金を貯金に回すことや、趣味・旅行に使うこともできます。
●初期費用や更新料が安いことも
人気のエリアでも線路沿いは敬遠されがちなため、敷金・礼金が低めに設定されている場合や、フリーレントがついている場合もあります。
●電車好きの人

電車が好きな人にとっては、線路沿いの家はむしろ楽しい環境になることもあります。
特に鉄道ファンや小さな子どもがいる家庭にはメリットが多いでしょう。
線路沿いのデメリットをデメリットと感じにくく、むしろ楽しめる生活ができるかもしれません。
メリット
●毎日お気に入りの電車を眺められる
窓から電車が見える部屋なら、お気に入りの車両や特急列車を間近で楽しめます。
●子どもが喜ぶ
電車好きの子どもがいる家庭では、窓から電車が見えたり近くに見に行けたりすることで、興味を引きやすく飽きずに過ごせるでしょう。
●趣味活動に便利
乗り鉄や撮り鉄を趣味にしている人にとって、電車の近くに住めるのは大きなメリットです。
駅が近ければ遠出の際にも便利なため、鉄道のある暮らしを満喫できます。
線路沿いの家が自分に合っているかどうか確認するのだ~

- ニッショー.jp
- サガッシーのなるほどふむふむ
- 線路沿いの家はやめた方が良い?後悔しないためのチェックポイント8選




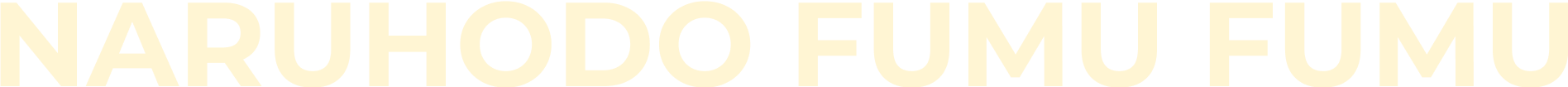

愛知・岐阜・三重で50年以上、地域密着の直営主義でお部屋探しを提供している不動産会社【ニッショー】が運営するWebマガジン。
思わず「なるほど〜」「ふむふむ」とうなずけるようなイチオシ情報をサガッシーとともにお届けします!











