キッチンパントリーの収納方法やアイディアをご紹介!上手な使い方のコツを知ろう

賃貸物件にパントリーがあると便利ですよね。
この記事では、パントリーには何を入れたら良いかや、収納方法のアイディアなど、パントリーを上手く使うためのコツを紹介しています。
-
パントリーとは?どんな種類がある?
-
パントリーのメリット
-
パントリー収納における3つの基本ルール
-
パントリーには何を入れる?収納例を紹介
-
パントリーに入れてはだめなもの
-
パントリーの上手な使い方のコツ!
-
パントリーって実際どう?使ったことある人の体験談
-
パントリーのデメリットを解決するアイディア
-
内見時にチェックすること
-
パントリーがある賃貸物件の探し方
パントリーとは「食品庫」のことです。
食品や飲料、日用品、調理家電、食器などあらゆるものを収納できるスペースです。
大抵はキッチンの近くにあるため、キッチンパントリーとも呼ばれます。
昨今の注文住宅ではパントリーを作る人も多く、広さや奥行き、設置場所などを考慮して作られています。
賃貸物件においても同様で、パントリーのある物件を見かけることも増えてきました。

パントリーの種類
パントリーにもいろいろありますが、賃貸物件においては、注文住宅ほどスペースに余裕がありません。
そのため、基本的にはキッチンの近くに壁付けタイプのパントリーを設けることが多いのではないでしょうか。
扉の有無についても違いがあり、オープンタイプと個室タイプがあります。
<壁付けタイプ>

賃貸物件では、壁付けタイプのパントリーが一般的です。
棚はあらかじめ設置されている場合が多いですが、可動式かどうかは物件によります。
デメリットとしては、収納スペースが足りない場合があること、奥のものが取りにくいため工夫が必要なことが挙げられます。
<ウォークインタイプ>

ウォークインタイプのパントリーは、スペースに余裕がある場合に作ることができます。
そのため、賃貸物件ではあまり見かけることはなく、希少だといえます。
中まで人が入れる造りになっており、通り抜けられるウォークスルータイプもあります。
パントリーのメリット
パントリーには大きく分けて3つのメリットがあります。
「収納力がある」
「キッチン周りがすっきりする」
「整理整頓できる」
さらに、これらのメリットによって得られることが下記の通りたくさんありますよ。
「収納力がある」ことで得られるメリット
・まとめ買いができる
・スーパーに行く頻度を減らせる
・飲料などを箱買いできる
・試してみたい食品を気軽に買える
・キッチン家電を収納しておける
・防災用の食品を買い置きできる
・キッチンに関係ないものも収納できる
・普段使わないものを入れておける
・日用品や郵便物も入れておける
・部屋が片付く
「キッチン周りがすっきりする」ことで得られるメリット
・キッチンがいつも片付いている
・キッチンに置くものを減らせる
・キッチンを広々と使える
「整理整頓できる」ことで得られるメリット
・ストック用品を探しやすい
・使うときにはすぐ出せる
・食材が取り出しやすいため料理が捗る
・ものの定位置ができるので片付けやすい
・出しっぱなしが減る
さらに言うなら、扉が付いているパントリーの場合はたくさん収納できる上に“閉めればすっきり見える”というメリットもあります。
パントリー収納における3つの基本ルール
パントリー収納には棚が付いていることが多いですが、何をどう収納すればよいのか、まずは基本的なルールを紹介します。
いずれの場合も、賞味期限が近いものは手前に置き、新しく買ったものは奥に入れましょう。
1.上段には軽いもの
もし落下しても大丈夫なように、上段には軽いものを入れましょう。
はしごを使うか背伸びをしなければ取れない高さの場合は、使用頻度の低いものを入れましょう。
賞味期限の長いものや、紙用品のストックなどに適しています。
-

・カップ麺
・キッチンペーパー
・ラップ
・アルミホイル
などを入れています。
2.中段にはよく使うもの
比較的よく使うものは、目線の高さである中段に入れましょう。
物の出し入れが活発なため、取り出しやすいことや、一目で在庫がわかるといったメリットがあります。
-

・パスタの麺やソース
・レトルト食品
・カレーやシチューのルー
・ツナ缶などの缶詰
・粉末だしやコンソメ
・お菓子作りに使う材料
などを入れています。 -

中段のうち一列は、
・文房具
・薬箱
・一時保管の郵便物
を収納しています。
3.下段には重いもの
重いものは下段に入れましょう。落下の心配がなく、棚にも負担がかかりません。
-

・醤油などの調味料
・鍋の素
・米びつ
・2リットルの水や飲料
・常温保存の野菜
などを入れています。
パントリーには何を入れる?収納例を紹介
基本的には何でも入れられるのがパントリーのメリットですが、具体的にはどんなものを入れているのか、ここでは例を紹介します。
実際にニッショーの社員に聞いたものも含んでいます。上記でも一部、実際の使用例を紹介しています。
<食品>
・カップ麺
・レトルト食品
・インスタントスープやみそ汁
・米びつ
・パスタの麺やソース
・缶詰
・ジュース
・お茶
・水
・酒
・コーヒー豆
・お菓子
・食パン
・非常食
<日用品>
・食器
・文房具
・薬箱
・郵便物
・取り扱い説明書
・キッチンペーパー
・ラップ
・ボックスティッシュ
・キッチン周りの清掃用品
・ゴミ袋
・古新聞
・花瓶
・エプロン
・マスク
・災害用緊急袋
・お菓子作りの道具
・お弁当グッズ(弁当箱、水筒、ランチバッグなど)
・クーラーボックス
・寿司桶
・オーブンの天板
<家電>
・ミキサー
・コーヒーメーカー
・カセットコンロ
・トースター
・オーブンレンジ
・ホットプレート
・土鍋
・掃除機
パントリーに入れてはだめなもの
パントリーには何でも収納できるとはいえ、入れない方が良いもの、入れてはだめなものもあります。
以下のものについては、うっかり収納してしまわないように注意しましょう。
賞味期限の短いもの

たとえ常温保存できるものであっても、賞味期限がすぐにきてしまうようなものは、パントリーには入れない方が良いでしょう。
どうしてもパントリーに入れたい場合は、対策をしましょう。
・目につきやすい中段に入れる
・賞味期限が短いものの専用ボックスを作る
・賞味期限が目立つようにメモに書いて貼っておく
生鮮食品など腐りやすいもの

野菜、鮮魚、精肉のほか、加工肉やチーズなども基本的には冷蔵庫で保存した方が良いでしょう。
湿気に弱いもの

玉ねぎやじゃがいもなど一部の野菜は常温保存できますが、梅雨時など湿気の多い季節にはパントリーに収納しない方がよいでしょう。
その他にも、湿気に弱い食品はパントリーでの保存に向かないため注意しましょう。
一度開封したもの

一度開封した食品で、個包装でないものは、パントリーから移動させ冷蔵庫などに保管しましょう。
開いた袋の口から虫などが混入する可能性もありますし、中身がこぼれてパントリーが汚れてしまう原因にもなります。
一度に使いきれない小麦粉などは要注意です。
ダンボールに注意!
ダンボール箱に入れたまま、パントリーに保管するのは止めましょう。
中見が何であるかに関わらず、ダンボール自体をゴキブリが好むため、虫が苦手な方は特に注意が必要です。
実家からの仕送りやネット通販で届いたものはダンボールに入っていることが多いと思いますが、すぐに箱から出し、中身だけ収納するようにしてください。
パントリーの上手な使い方のコツ!
ここからはパントリーに収納するときのコツを紹介します。
まずは事前準備として以下のことを考えてみましょう。
・「何」を入れるか決める
・「どこ」に入れるか決める
・「どう見せたいか」決める
・パントリー内の寸法を測っておく

収納したいものをリストに書き出してみるか、並べてみるなどして、まずは入れたいものがどれくらいあるかを把握しましょう。
次に、どこに入れるかを大体決めてみます。
最後に、どんな見た目にしたいかを決めましょう。
例えば、いつお客さんに見られても良いような見た目にしたければ、中身が見えにくい収納ボックスに入れた方が綺麗です。
反対に、機能性重視という場合は、一目で何が入っているかわかる、半透明の収納ボックスの方が使いやすいですよね。
これらのことを決めた上で、収納グッズを買いに行くと良いでしょう。
●収納グッズは必須

備え付けの棚があるとしても、収納グッズは必須といえます。
100円ショップでも十分揃えることができますし、細かい小さめの入れ物などは100円ショップの方がむしろたくさんあります。
また、デザインがおしゃれなものも増えています。
●取っ手のあるもの

収納グッズは取っ手のあるものが便利です。
または、指をひっかけてすぐに引き出せるものが良いでしょう。
下段であれば、キャスター付きのものでも良いですね。
●奥行のあるもの

中には、奥行きがあるパントリーもあります。
しかし奥のものが取り出しづらいと、在庫があるのに気づかなかったり、知らない間に賞味期限が切れてしまったりします。
そのため、収納グッズを買うときも、なるべく奥行きがあるものか、縦に2つ収納ケースを入れるなどして奥に空きスペースができないようにしましょう。
●色やシリーズはそろえる

色やシリーズを揃えておくと、見た目が良いだけでなく、スペースを余らせることなくぴったりと入れることができます。
そのためには、もちろん事前に寸法を測っておくことも大事です。
余分なスペースがあると、収納ケースとケースの間に食品がはさまれてしまい、雑然としたパントリーになりがちなため注意しましょう。
●半透明なもの、中身が見えやすいものを
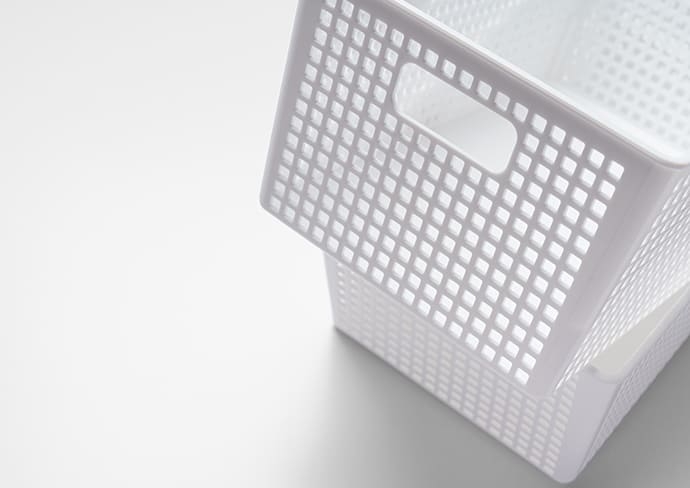
一目で何が入っているかわかりやすくするためには、半透明なものや、高さがあまりなく中身がのぞけるくらいの収納ケースがおすすめです。
網目状のかごであれば見やすいですが、粉末のものがこぼれたときは掃除の手間が要るので気をつけましょう。
●見えない収納ケースであれば、ラベルを貼る

中身が見えないもの、高さのある収納ケースを使うとおしゃれに収納できますが、在庫管理は少々しづらくなります。
そのため、中身の見えない収納ケースを使いたい場合は、ラベルを貼ると管理が楽になります。
例えばマスキングテープであればすぐに張り替えられますし、はがしやすく、品目追加もしやすいです。
●突っ張り棒や、棚の上部に付けられる収納棚を使う

棚の高さが固定である場合や、頻繁に高さを変えるのが面倒といった場合には、棚と棚の間の上部にデッドスペースができてしまうことも。
その際は、突っ張り棒を使用し、間にもう一段収納スペースを作ることができます。
他にも、棚の上部に付けられる吊り下げワイヤーバスケット・ワイヤーラックなどの収納グッズを使うと、スペースを無駄なく有効活用できます。
●ブックエンドやクリップを活用
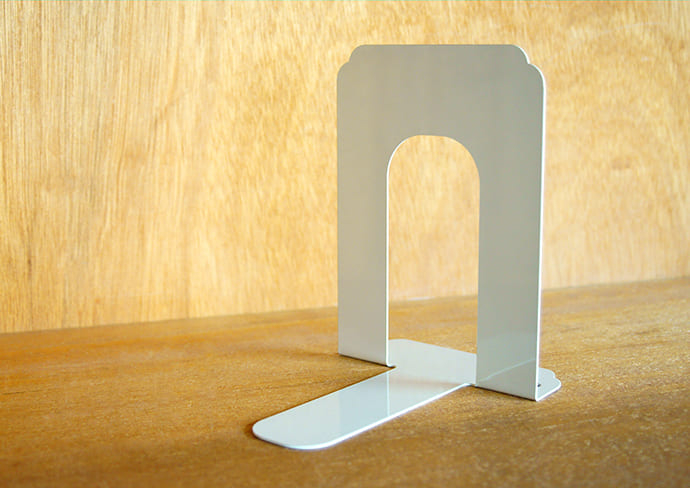
収納ケースを使っていても、中見が減ってきたときなどに食品が倒れてしまうことがあります。
その際には、ブックエンドを使うと立った状態で収納できます。
または、クリップなどでまとめて止めておいても良いでしょう。
パントリーって実際どう?使ったことある人の体験談
パントリーを使ったことのあるニッショー社員に、実際の使い心地や失敗談などを聞いてみました。

パントリーの失敗談
・上部はあまり使わなくなる
・重たい物を置くと板が反ってしまう
・たくさん入るからといって入れすぎると賞味期限切れが多発する
・何を置いたか忘れてしまって同じものを購入
・奥にしまいすぎて在庫切れに気づかない
・奥から開封したものが出てくる
・奥の方が湿気やすい
・奥に収納したものを取り出すのが面倒で使わなくなり、埃をかぶる
・きれいに収納しないとごちゃごちゃした見た目になる
・100円ショップなどの収納グッズは必須だが、かなりの量が要る
・最初に適当に入れすぎてどこに何があるかわからない
こんなパントリーがあると良い
<パントリー自体>
・なるべく目立たず、収納力が高い
・中が見える、スケルトン
・冷蔵庫やキッチンに近い
・床下収納付き
<棚について>
・可動棚
・スライド式の棚
・高さ調節可能
・上段は昇降式
・ラック収納が5段程度
・奥行きがあるもの
<広さについて>
・ウォークスルーできる
・ウォークインクローゼット並みの大きさ
・1.5帖は欲しい
パントリーはこんな人には不要かも
・まとめ買いや買い置きをしない人
・在庫管理が苦手な人
・整理整頓が苦手な人
・システムキッチンなど他の収納スペースで足りている人
パントリーのデメリットを解決するアイディア
パントリーにも下記のようなデメリットがあります。
ここではパントリーのデメリットを解消するための方法を紹介します。
同じものを買ってしまう
・家族と買いものリストを共有する
・在庫管理表を作る
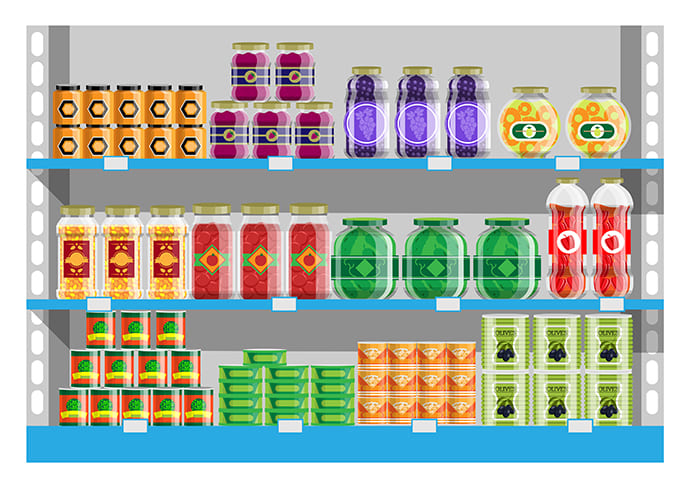
パントリーにあるものを把握していないこと、家族間で買い物をする人が自分以外にも複数いて、同時期に買ってきてしまうことが考えられます。
対策としては「買い物リストを共有する」こと、パントリー内に「在庫管理表を貼っておく」など一目で在庫がわかるようにしておくと便利です。
また、紙に書くのが面倒な場合は、スマホアプリを活用するのも有効です。
食品を無駄にしてしまう
・まとめて買うのは1箱まで、など自分ルールを決める
・在庫管理表で賞味期限を把握しておく

まとめ買いができるのがパントリーのメリットですが、一度にたくさん買いすぎてしまうと、消費しきれずに賞味期限が過ぎてしまうことがあります。
スーパーに「1人1つまで」などと書いていない時でも、自分ルールとして2つ以上買わないなどと決めておくようにしましょう。
また、賞味期限を把握していないことも食品を無駄にしてしまう原因の一つです。
これについても在庫管理表に合わせて記載しておくことで、把握しやすくなります。
整理整頓が面倒
・パントリー消費DAYを作る
・一目見てどこに何があるかわかるよう収納する

整理整頓が面倒な人は、定期的にパントリーの中のものを減らすため、月に1度と決めてパントリー内だけで献立を考える「消費DAY」を作りましょう。
その際に、賞味期限の切れそうなものや、在庫が切れそうなものを把握することができます。
また、整理整頓を頻繁にしなくても良いよう、最初に収納するタイミングで、一目で何があるかわかるように収納できるかが大事です。
どうしても時間が経つとぐちゃぐちゃになってしまうという人は、一度全部出してから入れ直すと良いでしょう。
湿気や臭いがこもる
・定期的に扉を開けて風を通す
・除湿剤を置く
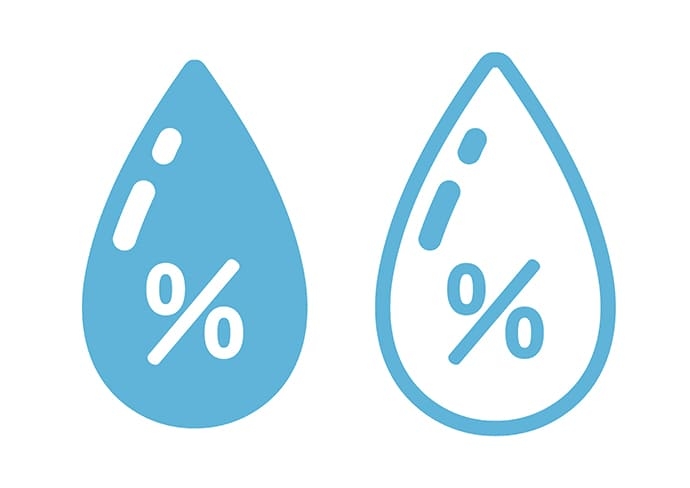
オープンタイプでないパントリーの場合は、中にものがたくさん入った状態でずっと締め切っていると湿気や臭いがこもってしまうことも。
定期的に扉を開けて風通しを良くしたり、市販の除湿剤を置いたりして対策しましょう。
デメリット解消方法のまとめ
・家族と買いものリストを共有する
・在庫管理表を作る(賞味期限も把握しておく
・まとめて買うのは1箱まで、など自分ルールを決める
・パントリー消費DAYを作る
・一目見てどこに何があるかわかるよう収納する
・定期的に扉を開けて風を通す
・除湿剤を置く
内見時にチェックすること
賃貸物件を内見する際には、パントリーの広さなどをしっかり確認しましょう。
ここでは、具体的なチェック項目を紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
・パントリーの位置
・パントリーの広さ
・棚の有無
・扉の形状、開けやすさ
・照明があるか
-
- パントリーの位置
- 間取り図であらかじめ把握できるとは思いますが、内見した際には、キッチンからどのくらいの距離にあるか、離れすぎていないかなど、実際に料理をしているイメージで動いてみると良いでしょう。
-
- パントリーの広さ
- パントリーの全体的な広さや幅・奥行きをチェックし、物が取り出しやすいかどうかや、収納する際に窮屈でないかなどを確認しましょう。
-
- 棚の有無
- 備え付けの棚があるかどうかや、棚の位置が変えられるかどうかをチェックしましょう。
棚がない場合は、自分で用意する必要があります。
-
- 扉の形状、開けやすさ
- 扉に多いのは「引き戸」または「折れ戸」ですが、「開き戸」の場合もあります。
また、扉を開けたときに通行の邪魔にならないかも確認しておきましょう。
-
- 照明があるか
- パントリーの中に照明があるかどうか確認しましょう。
照明がなくても十分明るい場合もありますが、キッチンの照明だけでは足りない場合、センサー式の照明を置くなどして対策する必要があります。
パントリーがある賃貸物件の探し方

賃貸物件でパントリーのある物件を探す方法は主に3つあります。
-
- 1.絞り込み条件で「パントリー」にチェックを入れて探す
- 絞り込み条件に「パントリー」がある場合は、チェックを入れて探してみましょう。
エリアや家賃などを指定すれば、希望の物件に出会いやすくなります。ただ、賃貸ではまだ物件数が少ない場合もあります。
-
- 2.「パントリー」代わりに使えそうな収納のある物件を探す
- パントリーとして使いたい場合には、使い勝手の良い場所に収納があれば良いのです。
したがって、探しにくい方法ではありますが、間取りや室内写真からパントリーの代わりに使えそうな物入を探す方法もあります。
パントリーという言葉は近年になって使われ始めたため、築年数が古い物件にはパントリーという設備が登録されていないこともあります。
備え付けの棚がない場合は、突っ張り棒やキャスター付き収納ワゴンなどを設置して、使いやすくしましょう。
-
- 3.ニッショーのタグ検索「料理がしやすいキッチン」から探す
- ニッショーなら、タグ検索「料理がしやすいキッチン」の賃貸物件を探すことができます。
該当する条件には「システムキッチン+3口コンロ」や「パントリー」があることなどが挙げられます。
そのため、総合的に料理がしやすいキッチンのある物件が探せるだけでなく、パントリーがある物件も見つけやすくなっています。
パントリーや収納があると、便利なのだ!

よくある質問
パントリーとは何語でどういう意味ですか?
- パントリーは英語で「pantry」といいます。
意味は「食品庫」で、キッチンの近くに設けられた、食品や食器、調理道具などを収納しておけるスペースのことです。
ちなみに語源は古フランス語の「paneterie」で、パンを保管するスペースのことです。
パントリーのメリットとデメリットは?
- パントリ―の大きなメリットは、以下の3つです。
・収納力がある
・キッチン周りがすっきりする
・整理整頓できる
これにより、まとめ買いができたり、試してみたい食品を気軽に買えたり、防災用の食品を買い置きしておけたりします。
その他にも、キッチンを広々と使えたり、食材が取り出しやすくなったり、料理が捗ったりと、家事のしやすさや時短につながるメリットも得られます。
反対にパントリーのデメリットは以下の通りです。
・同じものを買ってしまう
・食品を無駄にしてしまう
・整理整頓が必要
・たまに見直したり掃除したりするのが面倒。
・湿気や臭いがこもる
しかしこの記事では、パントリーのデメリットを解消するための方法を紹介しているため、参考にしてみてください。
パントリーとキッチンストッカーとの違いは何ですか?
- パントリーとキッチンストッカーの用途はほぼ同じで、食品や飲料などを収納しておける便利なスペースです。
パントリーは最初から部屋に設けられたスペースであるため、移動はできません。
それに対し、キッチンストッカーは家具または収納アイテムの一種で、サイズによってはパントリーの中に設置して使うことができます。
また、キッチンストッカーのサイズは様々で、食器棚ほどの高さのあるものもありますが、それ自体移動することができます。
中にはキャスター付きでキッチンワゴンのようなストッカーもあります。
パントリーがあると良いのはどんな人?反対に不要なのは?
- パントリーがあると良いのは以下のような人です。
・特売品を買うのが好きな人
・防災用に買い置きしたい人
・ローリングストックをする人
・おすそわけなどいただきものをもらうことが多い人
反対に不要なのは以下のような人です。
・まとめ買いをあまりしない人
・在庫管理が苦手な人
・システムキッチンなど他の収納スペースで足りる人
パントリーがないときはどうすれば良いですか?
- パントリーがないときは、収納力の高い家具などで代用するか、パントリーとして使える他の場所を探す方法があります。
・システムキッチンのある物件に住む
・キッチンストッカーや大きめの食器棚を購入する
・室内にある他の物入をパントリーとして使う
その他、床下収納や玄関収納でも、キッチンの近くにあるとは限りませんが、食品や飲料などをストックできるスペースとして使うことができます。
- ニッショー.jp
- サガッシーのなるほどふむふむ
- キッチンパントリーの収納方法やアイディアをご紹介!上手な使い方のコツを知ろう




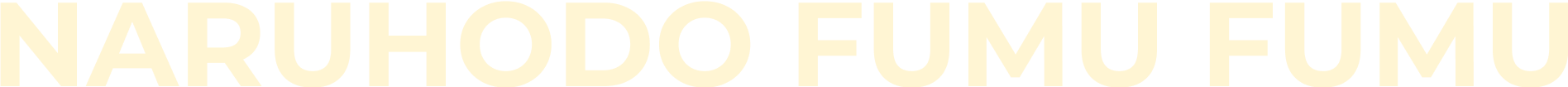

愛知・岐阜・三重で50年以上、地域密着の直営主義でお部屋探しを提供している不動産会社【ニッショー】が運営するWebマガジン。
思わず「なるほど〜」「ふむふむ」とうなずけるようなイチオシ情報をサガッシーとともにお届けします!











