賃貸物件における「残置物」とは?契約前に確認すべき3つのポイント

残置物とは、元の入居者が退去する際に残していった物のことをいいます。
ここではまず、残置物についての基本を押さえておきましょう。
残置物の読み方
残置物は「ざんちぶつ」と読みます。
聞きなれない言葉ですが、賃貸契約や不動産関係の書類で使われることが多い専門用語です。
残置物は誰が置いていくのか
残置物はなぜ発生してしまうのでしょうか。元々住んでいた人によって理由はさまざまです。
-
- ■大家さんが住んでいた物件を貸し出す場合
- 大家さんが使用していた家具や家電、DIYをしたアイテムがそのまま残っていることがあります。
-
- ■前の居住者が残していく場合
- 前の居住者が退去するにあたり、その部屋で使っていたけれど引っ越し先には不要な家具や家電を置いていく場合があります。
-
- ■自分が退去する際に残していく場合
- 自分が退去する場合にも残置物を発生させてしまうことがあります。うっかり処分するのを忘れていってしまった場合も残置物となります。
残置物の例
残置物には以下のようなものがあります。

家具(ソファ、テーブル、食器棚など)
家電(冷蔵庫、エアコン、洗濯機など)
その他(カーテン、照明器具、風呂の蓋、ランドリーパイプ、庭の物置、DIYで取り付けた棚やフックなど)
残置物はどんな物件に多い?
残置物は、前の入居者が比較的長く入居していた場合に多く発生することから、以下のような物件に多いです。
-
- 分譲賃貸
- 元々個人の所有者が住んでいた場合、家具や家電が残されることが多いです。
-
- 貸家
- 築年数が古い貸家は特に、長く使用していた家具や庭で使用する物などが放置される場合があります。
-
- 店舗・事務所
- 業務用の什器(じゅうき)や設備が残されていることがあります。
残置物と設備はどう違う?
残置物
・前の入居者が残していったもの
・故障や修理の費用は借主が負担することが多い
・取り扱い方は物件ごとに異なる
設備
・貸主が物件に備え付けたもの
・貸主が管理・修理の責任を負う
・借主が利用する場合でも、故障時には貸主が対応する
・賃貸契約書に記載されている
エアコン・照明器具は残置物です
エアコン・照明器具は設備ではありません
エアコン・照明器具は残置物のため設備ではありません
エアコン・照明器具はサービス品です
これは簡単に言うと「修理費や交換費用などの費用は借りる側(借主)が負担してください」という意味になります。
そのため、これに続く文章として「交換・修理費等は借主負担です」といった内容が記載されている場合が多いです。
残置物を撤去したい!費用は誰が出す?
残置物がある場合、撤去したいという人は多いですよね。その際、費用負担が誰にあるのかが問題になります。
一般的には以下のようなケースが考えられます。
■借主(入居者)が負担する
借主が残置物を撤去したい場合、その費用はたいてい借主が負担することになります。
残置物を撤去せず使うという場合も、故障や交換、維持管理にかかる費用は借主が負担しなければならないことが多いです。
■貸主(大家さん)が負担する
残置物については、貸主が修理費を負担する必要はありません。
しかし、物件に対する責任はあることから厚意で負担してもらえる場合があります。
また、特に契約書で取り決めをしていなくても借主の要望、相談に応じ、費用を負担してくれることも。
ただし、貸主次第であるため必ず費用を負担してもらえるかはわかりません。
残置物のよくある取り扱い方
ここでは「残置物を撤去したい」場合のほかにも、よくある残置物の取り扱い方を紹介します。
①撤去が可能
貸主が許可していれば、借主が撤去、処理することができます。
費用を誰が負担するかは契約書や話し合いで決まります。
②使用はできるが修理費は借主負担
借主が使用してよいが、万が一故障した場合の修理費用などは借主負担になる場合があります。
例えば、古いエアコンが残置物として残されていると、このようなケースが多いです。
③撤去不可かつ使用もできない場合
残置物をそのまま置いておかねばならないこともあります。
大家がいずれ戻ってきた際に使用したいという場合などが考えられます。
この場合、借主が何も手を加えられないことが一般的です。
④貸主が所有権を保持した状態で使用可能
貸主が残置物の所有権を放棄しないままで、借主に使用を許可するケースもあります。
この場合、借主の使用状況に応じたルールが決められている場合があります。
⑤特定の条件付きで利用可能
残置物を使用するために、クリーニングや整備が必要なことがあります。
この場合、費用は借主負担になるか、交渉次第で貸主と折半するなど事前の合意が重要となります。
⑥共同利用可能な物として扱う
例えば、アパートの共用スペースに残されている家具や設備が、全入居者で共有されるケースも考えられます。
利用方法については、貸主や管理会社の指示に従う必要があります。
残置物でよくあるトラブル
残置物をめぐるトラブルは意外と多いものです。よくある例を紹介します。
■借主が勝手に処分してしまった場合
残置物を借主が無断で処分すると、トラブルに発展する可能性があります。必ず貸主に確認してから行動しましょう。
■借主が許可なく使用してしまった場合
残置物を借主が自由に利用できないことがあります。
そのため勝手に使ってしまった場合にはトラブルとなり、損害賠償や修理費などが必要になることもあります。
■借主が残置物を破損してしまった場合
借主が残置物を破損してしまった場合には、その修理費を借主が支払わねばなりません。
契約書に残置物の管理責任が明記されている場合は、その内容に従う必要があります。
■敷金が返ってこない場合
このケースは、自分が退去する際に残置物を置いてきてしまった場合のトラブルです。
その場合、貸主が残置物の撤去費用を敷金から差し引くことがあります。
契約時に撤去費用について確認しておくことが重要です。
■清掃費や管理費を追加請求される場合
このケースも、自分が退去する際に残置物を置いてきてしまった場合のトラブルです。
残置物が多く、敷金で対応しきれない場合、清掃費や管理費を追加請求される場合があります。
引っ越し時には物件の状態を確認し、基本的には残置物を残していかないように心がけましょう。
契約前に確認すべき3つのポイント
賃貸契約書における残置物の取り扱いについて、契約前に確認しておくことが重要です。
1.契約書の内容
残置物が物件に残っている場合、それが利用可能かどうか、また使用条件があるのかを確認しましょう。
撤去を希望する場合は、入居するまでに依頼しなければならないケースもあります。
そのため、タイミングや条件について事前に確認しておくことが大切です。
2.内見時に実物をチェック
契約前に物件を内見し、残置物の有無や状態をチェックすることも重要です。
設備なのか残置物扱いになるのか、確認しておくと安心です。
また、写真や動画で記録を残しておくのも有効です。
3.気になることは事前に質問・交渉する
「これを撤去してほしい」「この設備は使用できるか」など、気になる点があれば事前に質問や交渉をしておきましょう。
使用できると思っていたが実際は違った、など契約後に後悔することのないよう、慎重な確認が求められます。
また、残置物を撤去をする許可を得ている場合も、実際に撤去する前と後に報告しておくと安心です。
まとめ
残置物のある物件は賃貸契約の際に、契約書をしっかり確認することが大事です。
契約書を見ても分からない場合は不動産会社や貸主に確認しましょう。
また、気になることや要望があれば事前に伝えておき、貸主と残置物の取り扱い方法について共有しておきましょう。
これにより、トラブルを未然に防ぎ、快適な賃貸生活を送ることができます。
「残置物」がある物件は、内容をよく確認するのだ~!
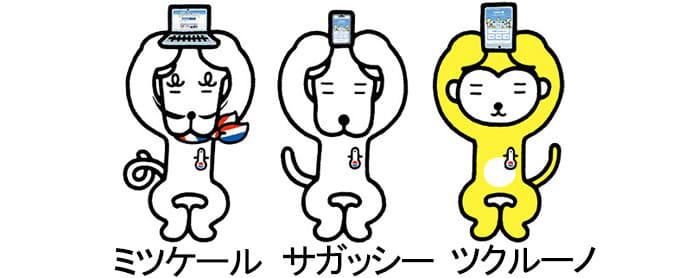
- ニッショー.jp
- サガッシーのなるほどふむふむ
- 賃貸物件における「残置物」とは?契約前に確認すべき3つのポイント




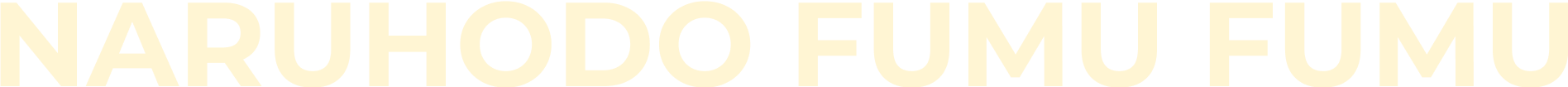

愛知・岐阜・三重で50年以上、地域密着の直営主義でお部屋探しを提供している不動産会社【ニッショー】が運営するWebマガジン。
思わず「なるほど〜」「ふむふむ」とうなずけるようなイチオシ情報をサガッシーとともにお届けします!











